金剛院。旧新義真言宗の常法檀林所
金剛院の概要
真言宗豊山派寺院の金剛院は、金龍山妙音寺と号します。金剛院の創建年代等は不詳ながら僧宥慶が開山、岩槻にあって金剛坊と称していたといいます。寛正年中(1460-1466)当地に移転し金剛院と改めたといいます。徳川家康関東入国後の天正19年(1591)には、寺領10石の御朱印状を受領、新義真言宗の常法談林所として近隣に数多くの末寺を擁していました。当寺の仁王門は桂昌院(徳川綱吉の生母)からの寄進と伝えられ、金剛力士像と共にさいたま市有形文化財に指定されています。武蔵国八十八ヶ所霊場33番です。

| 山号 | 金龍山 |
|---|---|
| 院号 | 金剛院 |
| 寺号 | 妙音寺 |
| 住所 | さいたま市岩槻区末田1899 |
| 宗派 | 真言宗豊山派 |
| 本尊 | - |
| 葬儀・墓地 | - |
| 備考 | - |
金剛院の縁起
金剛院の創建年代等は不詳ながら僧宥慶が開山、岩槻にあって金剛坊と称していたといいます。寛正年中(1460-1466)当地に移転し金剛院と改めたといいます。徳川家康関東入国後の天正19年(1591)には、寺領10石の御朱印状を受領、新義真言宗の常法談林所として近隣に数多くの末寺を擁していました。当寺の仁王門は桂昌院(徳川綱吉の生母)からの寄進と伝えられ、金剛力士像と共にさいたま市有形文化財に指定されています。
新編武蔵風土記稿による金剛院の縁起
(末田村)
金剛院
新義眞言宗、金龍山妙音寺と號す、京都仁和寺末にして檀林所なり、寺領十石の御朱印を賜ふ、開山の僧を宥慶と云、寂年を傳へず、當寺古へは岩槻にありて、金剛坊といひしを、寛正年中當地に移りてより金剛院と改め、堂塔以下造立すと云、本尊虚空蔵は長三尺許、弘法大師の作と云、
鐘樓。元禄三年鑄造の鐘なり
仁王門。棟札に元禄十年桂昌院殿御寄附の由を記す、
護摩堂。不動を本尊とす
經堂。一切經を蔵し十一面觀音を安置す、
稲荷社(新編武蔵風土記稿より)
金剛院所蔵の文化財
- 金剛院仁王門及び金剛力士像
金剛院仁王門及び金剛力士像
金剛院は、奈良長谷寺の新義真言宗豊山派に属し、金龍山妙音寺という。開山は僧宥慶、初め岩槻にあって金剛坊と称したが、寛正年中(一四六〇~一四六六)に当地に移り金剛院と称した。
天正十九年(一五九一)、徳川家康から寺領十石の御朱印を賜り、またかつては常法談林として多くの僧侶を教化し、武蔵国移転寺十一か寺の一として由緒ある格式を誇っていた。
仁王門は、元禄十年(一六九七)桂昌院の寄進と伝え、簡素な造りではあるが、三段に組込まれた垂木や屋根の形などに当時の優雅な名残を伝える建築である。屋根瓦の大部分を失っているのは惜しいが、堂々とした風格をもち、中央に心山和尚の筆になる「金龍山」の門額を掲げる。
門の左右に配された阿吽形の金剛力士像は、共に江戸時代前期の作と思われ、寄木造り、玉眼嵌入、胸上で着手式とし、体幹部は左右二材を基本とし、各々補材を充てている。仕上げは下地漆の上に不着せを行ない彩色されている。
阿形は左手に金剛杵を執り、右手を力いっぱい広げて降ろし、吽形は左手を広げて挙げ、右手は強く握って降ろすという一般の形であるが、胸や腕、背中の筋力の表わし方や、均整のとれた姿態はこの期のものとしてすぐれた出来栄えを示している。
昭和五十六年五月十二日 市指定文化財となる。(岩槻市教育委員会掲示より)
金剛院の周辺図
参考資料
- 「新編武蔵風土記稿」
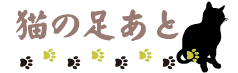
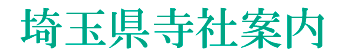
 金剛院本堂
金剛院本堂 金剛院鐘楼
金剛院鐘楼